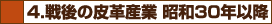
2.成長期(昭和40年代)
昭和40年(1965)に入り、日本経済は前年の「オリンピック景気」に引き続き、同45年7月までたくましく成長を続けた「いざなぎ景気」に引き継がれた。同42年~44年度の国民総生産(GNP)は実質年率13%を超える高成長率となり、同42年1,140億米ドルを記録し、資本主義のなかで第3位に到達した後、同43年には1,428億米ドルとなってアメリカに次ぐ第2位へと躍進を遂げた。この間、わが国の労働生産性は87%も伸び、高度成長の波に乗ってカー、クーラー、カラーテレビが「新三種の神器」ともてはやされた。これらに象徴されるように国民生活における消費財の需要が著しく伸びた時期である。これは皮革産業にとってもよい影響を及ぼした。
●ガラス張り製革法の普及
昭和30年(1955)代から続いた板張り銀付き革から、次第にガラス張り革(銀面摺り塗装仕上革)の比較的硬目の革の需要へと市場の動きが変わってきた。大手タンナーではいち早くガラス張り乾燥法も取り入れていたが、この変化に対応して各地の企業でもジュラルミン板乾燥室とペーパーロール機(銀面摺り機)の設備を設けるところが多くなってきた。
ガラス張りミート調革の普及は同45年(1970)後半頃まで続いた。
その後、ついで光もののエナメル革のファッションが始まった。各工場ともエナメル革の生産に活況を呈し、エナメル設備のない工場は速乾性エナメル革の生産をするなど、市場はエナメル革一色となった。
●合成靴底の普及
昭和40年(1965)代初頭に皮革業界を襲った一つの大波は、合成靴底の進出であった。合成ゴムの技術の進歩によってその性能が著しく向上し、安くて耐久性のある靴底を大量に作ることが出来る様になった結果、靴底はこの合成底にたちまちとって代わられたのである。メーカー自身の近代化も、この交替に拍車をかけた。すなわち、製靴業界では従来の家内工業的生産方式から機械化による大量生産方式へと移行が進み、能率を重視する機械靴メーカーは高価で扱いにくい革底よりも、安価で機械的製造に向く合成底を選んだ。
●アメリカの貿易自由化要求の激化
一方、海外からは皮革関連品目の貿易自由化の要求が次第に高まってきた。即ち昭和44年(1969)秋の日米経済貿易交渉の席で、今後の日本の皮革市場の有望性に着目したアメリカは皮革の自由化を強く要望し、わが国はこれを受け入れて同46年6月、エナメル革、靴部品、革衣料の三品目に限って自由化に踏み切った。しかしその後は、年々厳しくなる自由化攻勢を業界一丸となって阻止し続けた結果、牛馬革、山めん羊革、革靴は石炭や農産物などとともにわが国最後の非自由化品目となった。
また同40年、国産の人工皮革がクラレから初めて発売され、製革業界に大きな心理的な不安をもたらせた。
●ブーツの流行と原皮相場の暴騰暴落の波
昭和42年には初めてブーツが流行し、数年間続いた。原皮相場は、同40年には当時としては一時的最高値をつけ、同42年に、そして同47・48年にも最高値がくり返された。そして革価格の高騰に伴う需要低下およびアメリカの原皮供給の過剰感も作用して、その後は暴落が続き、同49年末は業界人の常識をはるかに超える安い相場となり、北米産バットで1ポンド当り10セントに至った。業界は商況不振と激変への対応に苦労した。
次いでこの当時、内外経済に多大な影響を与えたのは、ドルと石油の問題である。
●ドルショックと為替変動相場制
昭和46年(1971)8月世界経済は突如のドルショックに襲われた。このショックはアメリカ、ニクソン大統領の声明が発端となったもので、ドル防衛策と主要各国への平価切り下げ要請を主な内容とし、これまでの固定相場制を基盤とする経済秩序を覆すものであった。
このショックに対処するためヨーロッパ各国は同月23日に、日本は28日にそれぞれ変動相場制に移行し、その後スミソニアン協定を経て主要各国の通貨はドルに対して切り下げられ(円は1ドル=308円16.88%の切り上げ)固定相場制となったが、同47年6月から48年2月にかけ各国とも再び変動相場制の採用に踏み切った。
●オイルショックと製革業界
昭和48年(1973)10月と12月の2度にわたりOPEC(石油輸出国機構)により、原油価格の大幅な引き上げが行われ、同時に5%の生産削減と親イスラエル諸国の前面禁輸または供給削減を含む石油戦略が打ち出され、第一次オイルショックが起きた。
当時の日本は一次エネルギーの77%が輸入石油で賄われ、その85%を中東諸国に依存していた。経済の高度成長も安価で豊富な中東石油のもとに築かれたといっても過言ではなかった。ところが同49年1月から基準原油の公示価格が1バーレル=11.65ドルに引き上げられた。これは前年10月以前と比べると約4倍高の価格であった。
この原油価格の急騰により諸物価が暴騰し、同48年(1973)11月にはトイレットペーパーをはじめ、全ての商品の品不足、買い占めパニックが起こった。いわゆる「狂乱経済」となった。
皮革業界も重油、灯油、ガソリン等の燃料類と皮革仕上げ剤のシンナー、クリヤー類の品不足と暴騰により皮革の生産に大きく支障をきたし、一時は大パニック状態となった。同49年中頃に入り品不足パニックは一応おさまったが、しかし諸物価は高値になった。値上がりを見込んで売り惜しんでいた全ての商品も一挙に市場に出回り、逆に物余り気味となった。
このオイルショックのあと、いわゆる「省エネ」が叫ばれ、大量消費、使い捨ての風潮から一転して「節約」へ、「買い控え」となって「モノ離れ現象」が定着した。
●設備近代化・協業化の推進
また昭和40年代は業界の体質改善についてもみるべきものがあった。
貿易・為替の自由化に続いて同42年以後は資本についても極力これを進めてきた政府は、同46年4月、自由化の遅れている皮革業界に対し本格的な行政指導に乗り出した。即ち、政府貸与の無利子資金を利用して中小タンナーの設備近代化、協業化を進めるという内容の業界構造改革案を示したのである。姫路・龍野を中心とする兵庫、和歌山の中小タンナーの多くがこの公的資金を活用し、それぞれ大規模な設備投資を行った。これにより、中小タンナーの生産能力は著しく改善され、大手タンナーとの企業格差は一挙に縮小した。しかしながら、需要を伴わない設備拡大のツケはすぐに回ってきた。同40年代末には供給過剰が目立ち始め、のちのちまで影響を残すことになった。
●輸入品の増大へ
さらに、この間昭和46年8月のいわゆるニクソン・ショック以後、政府は各種の輸入拡大措置を講じたため、同47年頃から海外製品の流入が著しく増加しはじめた。靴、カバン、袋物、小物などいずれも欧米の高級品が革製品の市場にも流れ込み、革市場ばかりか製品市場でも競争が一段と激化した。