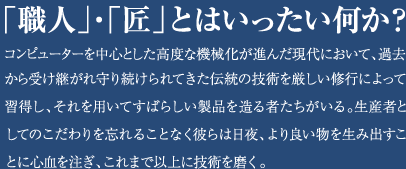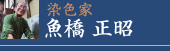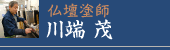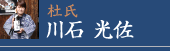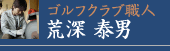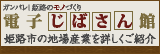姫路市船津町は、良質の粘土がとれることから古くから瓦造りが盛んで、特に文化2年(1802)に姫路藩御用瓦師であった小林又右衛門が船津町に窯を開いて以来、昭和初期まで多くの瓦製造業者が軒を並べ、「神崎瓦」の名で全国に知られたという。
時代の変化の中で業者の数は激減したが、今も船津町で伝統の「いぶし瓦」を作り続けているのが光洋製瓦で、そこで鬼師を務めているのが構井一巳さん。
播州では一般に道具師と呼ばれているが、鬼師とは城郭や寺院建築の鬼瓦や鯱瓦などの役瓦を作る職人のことである。
構井さんこの道に入ったのは19歳の時。
鬼師だった父の初代構井一巳さんに「やってみないか」と誘われ、「何とはなしにやってみようか」と思ったのがきっかけで、「オヤジも50歳を過ぎて、弟子が欲しいと思ったのかも知れません。それで深く考えることもなくこの道に…」と、構井さんは苦笑いする。
父に弟子入りし、修業の道に入った構井さんだが、師である父親は「ああせい、こうせいとは言わず、見とけよと言うだけ」だったという。
で、最初は型を抜いて作る簡単なものから修業を始め、ヘラの使い方や土の練り方などを学んだが、「力まかせにやれば良いというもんじゃないし、土の厚みをどれぐらいにすれば良いかが難しかった。薄くし過ぎると土が切れてしまうし、厚過ぎると焼成する時に(土の)中の方が焼け残って爆ぜてしまう。爆ぜると破片が飛んで、窯の中に入れている他のもんを壊してしまうので、オヤジがよく『お前の作ったもんの側では焼けん』とこぼしていました」と笑う。
型を使った仕事ができるようになると鬼瓦や鯱瓦などの「ひねりもん」に移った。
最初は父親が作った見本をそばに置いて、見よう見まねで作ったが、これにも父親は「そこがもう一つやのう、と言うぐらいで、どうせいとは言わなかった」そうで、「弟子としてはぬるま湯に浸かり過ぎた気もする」と振り返る。
そんな穏和な父であり師だったが、20年、30年とやるうちに、父の仕事ぶりが自然と頭に浮かぶようになったそうで、「オヤジはああしょったなあとかね。若い時分や腕のない時分はそれが頭に入らへんし、頭に浮かんでこなかった。それが修業を積むうちに、オヤジのやり方が頭に浮かぶようになり、それを自分なりに直したり、オリジナルなものができるようになった」と淡々と話す。
職人だけに道具も大事にする。
木のヘラなどは自分で山に行ってウツギやサクラの木を切り、自分の手に合うヘラを作る。
道具の90%は自分で作るそうで、一番愛着があるのは父親から譲り受けた鉄のヘラ。
40年ほど前に刀鍛冶が打ったもので、長い年月の間に摩耗し、3分の1ほどの長さにすり減ってしまっているが、この鉄のヘラが構井さん父子の仕事を見守ってきたのかと思うと、新たな感慨も湧いてくる。
「まだまだ勉強中」という言葉が何度も口をつく構井さんだが、難しいのは「間合い」だという。
鬼瓦や鯱瓦は屋根の上に飾られるもの。
下から仰ぎ見てどう見えるかが勝負であり、飾られる屋根の高さや勾配によって顔の向きや角度を変えなければならない。
それが難しいと言うのである。
また、構井さんはこれまでにも姫路城や京都の名刹などの役瓦を数多く手がけてきているが、「その時は満足できても、何年かたって見たらやっぱり満足できない。他の人がええやんかと言っても、自分に納得がいかん。腕がないなあ、限界かなあと思ってしまう。未だにその繰り返しです」と話し、「オヤジも70歳ぐらいの頃に、60歳ぐらいの時に作ったやつはもう一つやなあと言っていましたからね」と笑う。
職人の道には終わりがないということなのかも知れない。
とにかく取材の間にも人柄の優しさが伝わってくる構井さん。
そのせいか、構井さんが作る鬼瓦の顔には優しさが滲んでいると言われることが多いそうだが、「鬼ですから、ある程度の睨みは必要なんでしょうけど、悪いことをしていた鬼が改心してお寺を守るようになるですから、優しいところがあってもエエかなと。100人100色、いろんな顔があっても良いんじゃないですか」と。
強さに優しさが加わった構井さんの鬼瓦。
どこか得がたい味がする。